そして、
「どうせ買うなら自分だけのオリジナルが良い!」
なんてコダワリが出てくる気持ち、分かります^^
勢いで、オリジナル扇子も欲しいあなたへ、
市販の扇子の作り方から、
1点物扇子の作り方まで、
お教えしちゃいましょう!
[ad#co-1]
扇子の製造工程
❖扇骨加工
「扇骨」とは竹の部分のことで、
両外側の骨を「親骨」、内側の骨を「中骨」と言い、
それらを含めて扇骨と呼びます。
*胴切り(どうきり)
最初に竹の節を除いて、同寸法に切る作業を行います。
*割竹(わりたけ)
「胴切り」で同寸法に切られた竹を、
ナタで縦に割ります。
竹には上下と表裏があるので、
仕上げまで間違うことは許されません。
*アク抜き
均一な幅と長さに割られた青竹を釜で茹でて、
アクを抜きます。
アクを抜くのは後で色付けをするためです。
*せん引
湿っている竹の「ミ」と「カワ」の部分を、
二枚に剥ぎ分けます。
弾力と粘りがあり、腰も強いので、
京扇子は「カワ」の部分を使用します。
*目もみ
要の穴を骨にあける作業です。
一本ずつ開ける穴は、ほとんどズレがありません。
もしずれてしまうと、綺麗な扇に見えなくなります。
*あてつけ
要の穴に長い串を通し、
何百枚もまとめて板のようにします。
湿らせたその骨の側面を削り、
それぞれの扇骨の形に成形していきます。
*白干し
天日にさらし、
砂利の上で扇骨を乾燥させていきます。
*磨き
乾燥させた扇骨(中骨)を数枚にまとめ、
バフをかけて磨きます。
*染め・塗り
「染め」は扇骨を釜で茹でて、そこに染料を入れます。
「塗り」はハケを使い、扇骨に色を塗っていきます。
*末削(すえすき)
地紙に差し込む中骨の先端部分を、細く薄く削ります。
何本かにまとめられた骨を、機械で削っていきます。
*要打ち
「目もみ」によってあけられた穴に、
樹脂や金属を差し込み、要を打ちます。
これで扇骨は完成。
ちなみに、肝心要の「かなめ」は、
この要からきています。
❖地紙加工
夏扇子では3枚、舞扇子では5枚ないし7枚の
貼り合わされた和紙のことです。
*紙合わせ
↓
*乾燥、裁断
↓
*色引き・下地印刷
↓
*箔押し
↓
*上絵(うわえ)
❖折り加工
地紙を扇子の形のように、折れぐせをつける作業です。
*折り
↓
*中差し
↓
*万切り(まんぎり)
扇子の大きさに切り揃えます。
❖仕上げ加工(ツケ)
別々に仕上げられた、扇骨と地紙が合わさります。
*地吹き
↓
*中骨切り・糊付け
↓
*中附け(なかづけ)
↓
*こなし
*矯め(ため)・先づめ
↓
*親あて 親骨に糊をつけ、地紙を接着します。
セメ(帯)をつけて、扇子の完成!
すごい工程です!!
扇子の製造工程を見ると、
大切に使わないと!って改めて思いますね。
じゃあ、世界でひとつのオリジナル扇子、
その作り方って、どうなっているんでしょう?
扇子のオリジナル注文は1本からでも出来る
◆ハンカチやスカーフでリメイク!オーダーメイド 扇子
高かったけれど、もう使わない「スカーフ」や、
思い出の「ハンカチ」をリメイクして、
オリジナルの扇子を作ってくれるお店があります。
❖スカーフやハンカチを扇子にリメイク♪
オーダーする時の注意点。
手持ちのスカーフやハンカチを送ります。
送料は、注文側負担です。
生地の素材は、
- 綿
- 麻
- シルク
の天然素材100%のみです。
レースや刺繍が入っていたり、
箔プリントが入っている生地は使えません。
50㎝×50㎝で扇子2本出来上がります。
扇子袋付き1本は、50㎝×50㎝以上の生地が必要。
袋なしの扇子1点は、
縦25㎝×横45㎝以上の生地が必要です。
扇子と専用収納袋付き1セット
¥7,500 ¥8,100(税込み)
扇子のみ(収納袋なし)
¥6,500 ¥7,020(税込み)※送料等必要。
どんなでき上がりか…目立つことは間違いなしですね。
◆大島紬とは?
大島紬には、従来の泥染のほか、
- 植物染の糸で織る「草木染め大島」
- 色糸を用いた「色大島」
- 白泥で染めた糸で織る「白大島」
- 細い糸で織られた「夏大島」
などがあります。
大島紬は一部のものを除くと、
訪問着には使えないのですが、
購入すると、安くても10万円くらいから、
上は何百万円!なんてものはザラです。
カジュアルなシーンを格上げしてくれるのも紬。
披露宴の2次会などに着ると、
渋さと華やかさの両方があり、とても素敵です。
そこに老舗の“オリジナル扇子”が加われば、
もう無敵ですね~。
でも、どうやって注文すれば良いのでしょう?
扇子を老舗有名店で注文する方法や注意点
◆オリジナル扇子の注文方法
京都の老舗「白竹堂」さんの場合。
- 扇子地紙に直接、書く(描く)方法
- 原稿を元に印刷する方法
- 生地を持ち込み仕上げる方法
- 生地にプリントする方法
など、色々あります。
一度、問い合せをしてみましょう!
❖オリジナル紙扇子
墨や絵具を使って、
扇子の地紙に直接書き(描き)ます。
1本から製作可能。
まず地紙を買い、
書いた地紙を送り扇子に仕上げてもらいます。
地紙は『普通紙』と『片画仙紙』があります。
※墨は、膠(にかわ)などの色止め成分が入ったものを
使用してください。
※絵具は基本的に、アクリル絵具を使用してください。
水彩絵具は、色が移ってしまいます。
※落款は色うつりしますので、
扇子ができ上がってから押してください。
価格の例
普通紙を使って7寸5分25間(長さ約22.5cm、骨の数25本)
の扇子を、白竹で仕上げた場合。
1本の注文。
地紙代+仕上げ代=2,860円+税となり、
別途送料が発生します。
❖オリジナル生地扇子
手持ちの生地を扇子に仕上げてもらえます。
1本から可能です。
但し、生地の素材や厚みにより
仕上げられない場合もあります。
事前に持って行き、見てもらうことが条件となります。
価格:1本あたり 2,500円+税~
※詳しい価格は要相談です。
生地を見てもらって、見積りしてもらいます
オリジナル扇子に関する問い合せ
株式会社山岡白竹堂 特販部
京都市中京区麩屋町通六角上ル白壁町448番地
TEL:075-221-1206 FAX:075-221-2759
長持ちさせよう!扇子の開き方やマナーとは?
◆扇子の使い方
❖開け方
扇子の親骨を上に向け両手で優しく持ちます。
右手を要のあたりに添え、
もう片方で扇子の真ん中あたりを下から添え、
その親指で親骨を向かって、右側へ押すようにし広げます。
親指で押し少し開いたら、
両手で扇子をゆっくりと広げます。
一気に広げると、扇子を痛めてしまいますので
気を付けてください。
❖閉じ方
開いた扇子を両手で持ち、
右手で奥から手繰り寄せるように閉じます。
片手で閉じないで、扇子の折りにそって丁寧に閉じましょう。
扇子を閉じたら、しめ紙を忘れずに。
扇子を買った時に、扇子の上部を留めてある紙です。
扇子を使った後にはめておくと、
扇子の型崩れを防ぐ事ができますから、捨てないでね。
扇面も扇骨も、自然の素材を使って作られており、
水に弱いので、できるだけ濡らさないように使いましょう。
扇子はデリケートなので、大切に取り扱いましょう。
カバンに入れる時は、直接入れずに付属の袋に入れるか、
ハンカチなどに包んで入れましょう。
せっかくの扇子ですから、長持ちさせたいですね!
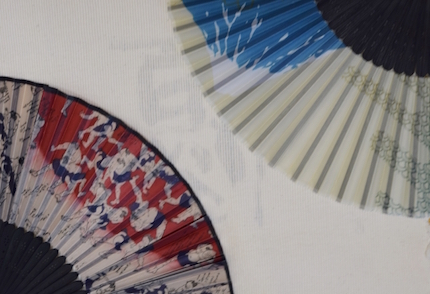



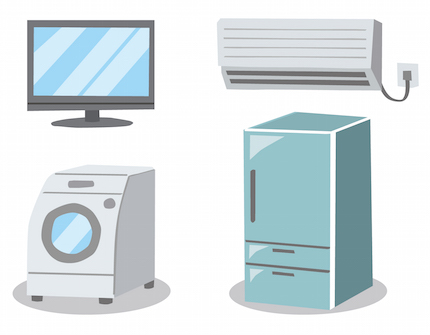
コメント