お正月といえば、
重箱に詰められたおせちが
定番だよね!
でもなんでわざわざ大変な思いをしてまで
ママやおばあちゃんは
おせち料理を作るんだろ~?
てゆうかハンバーグとかから揚げの方が
絶対美味しいじゃん(;゚д゚)
小学生の時って、
結構こんな事思ったりしちゃうんです^^;
昔からお正月の食卓の定番であるおせち料理には
どんな意味があるんだろ~
なんでハンバーグとかじゃダメなんだろ~
などという疑問を持った小学生たちのために!
おせち料理の歴史や由来、しきたりなどを、
わかりやすく解説していきますね!(^^)!
ちゃ~んと理解して
ママのお手伝いしてあげてね(o´∀`)b
おせち料理の歴史と由来について
え~まずはおせち料理の歴史や由来について!
社会のお勉強みたいだけど
分かりやすく解説できるように頑張りまーす!(^^)!
そもそもおせち料理を、
お正月に食べるお祝いの料理となったのは、
昔~昔の弥生時代がはじまり!
当時の人たちはお米とかの作物の収穫を、
季節ごとに神様に感謝しながら
お供えしてたんですよ。
この季節ごとっていうのが、
1年のうちに5回ある節句の時!
3月3日の桃の節句以外にも
・人日(1月7日)
・端午(5月5日)
・七夕(7月7日)
・重陽(9月9日)
っていう5つの節句があるんだけど、
この「五節句」の時には
必ず神様にお供えをするための料理が
作られてたの!
その神様にお供えしていた料理を
「節供(せっく)」
と言うんだけど、
この節供(せっく)が
今のおせち料理のはじまり^^
つまり原点なんですね!
中国では元旦になると
「節会(せちえ)」
と呼ばれる宴がひらかれるようになったんだけど
その時に節供(せっく)を食べていたんです。
節会(せちえ)で振る舞われたり
神様にお供えする料理を
人々は「御節会(おせちく)」料理と呼ぶようになり、
次第に名前が略されて
現在のおせちと言われるようになったんです。
また、お正月という1年の節目で1番大切な日に
おせち料理を食べるようになったのは
江戸時代がはじまりなんですよ。
ひとつひとつの食材に意味がある?重箱につめるしきたりはこんなところから
おせち料理に入っている食材って、
どんなものがあったか覚えていますか?
はっきり覚えてるのは、
子供が好きな食べ物が入ってない!
って事じゃない(゜Д゜;)?
だからおせち嫌~い(>_<)
っていう小学生も結構多いと思うんだけど、
おせち料理の食材には、
ひとつひとつにきちんとした意味があるんです!
それぞれの食材の意味や込められた願いを
ひとつひとつ見ていきましょうね^^
【数の子】
数の子っていうのは、
ニシンっていう魚の卵!
ニシンには卵がたくさんついてるんだけど
「卵が多い=子だくさんになる」事から、
子宝や子孫繁栄を願った、
縁起のいい食べ物なんです!
【田作り】
田作りっていうのは、
いわしの稚魚を干して甘辛く煮たもの!
昔はいわしを田植えの肥料にしていた事から
豊作を願う食べ物とされています。
【黒豆】
黒豆は、まめに働けるように願った食べ物。
一年中元気で、まめ(まじめ)に働けますように
と言う意味があります。
【たたきごぼう】
たたきごぼうは、
別名開きごぼうとも言われていて
運が開きますように願う意味があります。
【紅白かまぼこ】
紅白は縁起がいい・おめでたい
と言われています。
またあの半円形の形が、日の出に似ていることから、
お正月のおせち料理の一品として
採用されているんです!
赤色は魔除け、白色は清浄を
表しているんですよ^^
【伊達巻き】
伊達巻の「伊達」は豪華な・派手なという意味があって
繁栄や繁盛を願う意味が込められています。
また、形が巻物に似ていることから
勉強の成就を願ったものでもあるんです。
【栗きんとん】
栗きんとんは漢字で「栗金団」
と書くんです。
この字の通り金銀財宝を意味することから、
金運を招いてくれる縁起物だとされています。
【レンコン】
レンコンにはたくさんの穴が空いてますよね?
このことから
「先の見える1年になりますように」
と願われた縁起のいい食べ物なんです。
【海老】
海老って「つ」の字みたいに
曲がった形をしてますよね。
腰の曲がったような海老の形から
『腰が曲がるまで長生きできますように』
と、長寿を願う意味があります。
【昆布巻き】
これは「よろこぶ」の語呂合わせ!
無理やりな感じはするけど
漢字で書くと「養老昆布」って書いて
不老長寿をお祝いします!
【くわい】
くわいには大きな芽が出ます。
芽が出る=出世を願っていて
さらに「めでたい」という意味が、
込められるようになりました。
おせち料理の食材は
その家庭や地域によって違ってくるので
代表的なものの意味を解説してみました!(^^)!
ひとつひとつにちゃんと意味があり
ステキな願いも込められているんですよ♪
おせちの食材ひとつひとつの意味が分かったところで
最後は・・
「なんで重箱につめるのか?」
というのがこれまた疑問・・(´`:)
「お皿に盛り付ければいいじゃん!」
そんな声も聞こえてきそうだけど
重箱に意味や願いが込められた食材を
つめるという事は
「めでたさを重ねる」
という事!
重箱にも各家庭によって三段になってたり、
四段になってたりするけど、
正式な重箱は五段になっているものなんですよ!(^^)!
しかも一番下、つまり五段目には
何も入れずに空っぽにしておくんです!
その理由は
『神様から授かった福を詰めるため』
だったり、
『今は十分幸せだから、未来の幸せが最後の五段目に詰められますように』
という家族の願いが込められているからなんですね(o´∀`)
重箱にもちゃんとした意味があるなんて、
私たちは毎年、とっても縁起のいいものを目にしたり
口にしたりしてるんですね^^
まとめ
お正月のおせち料理って、
子供が好む食材は海老くらいしか入ってないじゃん!
って思ったりしちゃうけど、
ちゃんとした意味や理由があるから
おせち料理の食材代表として
重箱に詰められているんですよ^^
家族一人一人の健康や幸せを願ったおせち料理♪
食材に込められた願いを理解しながら
ママのお手伝いしてあげて下さいね(o´∀`)b
「そんなに入れるものあったっけ?」
って思っちゃうけど、
重箱は五段重で、詰め方にもしきたりがあり、
重箱の一段目~四段目までを上から順に、
一の重、二の重、三の重、与の重、
と呼びますが、
五段目は神様から授かった福を詰める場所として、
空っぽにしておきます。
新しい年を祝うおせちは神様への供物であり、
その品々のひとつひとつに意味が込められていると同時に、
おせち料理を詰める重箱にも、
「めでたさを重ねる」という意味で、
縁起をついだものが詰められています。
尚、お重の中身「おせち」は地方や家庭ごとに様々です。



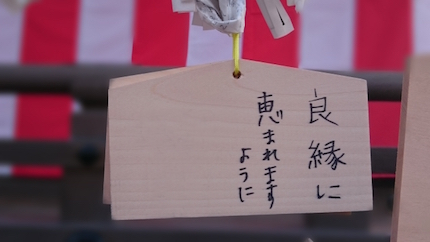
コメント